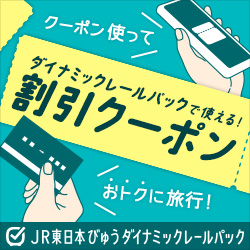都知事時代のあれこれ、タイトルから想像して、震災時に東京都から消防ヘリを気仙沼に飛ばし「救出」したという、自慢話を綴ったエグイ本なのかな、と思われるかもしれません。
が、むしろ、本書の内容的には、「避難」「脱出」「自助、共助」の方がふさわしいものでした。
これまでの津波の歴史と立地条件から、子供たちを守るために、震災前から、毎月避難訓練を実施していたという保育園園長や保育士たちの毅然とした態度と行動力。
いかに、常日頃の訓練、近隣との協力関係が重要か、改めて再認識させられます。
また、446人が限られたスペースの公民館に避難し、「2階ではだめだ、もっと上へ」という早めの判断に従い、少ないながらも公民館の備蓄資材があり、さらにコミュニティを形成する、働き盛りの男手がいたことで、年寄や子供たちを、より安全な場所へと導くことができたという「幸運な」条件が重なって、救助まで持ちこたえられた面はあると思います。
ただ、ネットの有用性は間違いないのですが、例えば仙台のある場所では、地震発生30分で、メールも電話もつながらなくなりました。被災直後の情報発信が、携帯、ネットですべて解決できるとは思わない方がいい、という事だけは、強く訴えたいところです。
東京など大都市の災害では、停電や物理的な基地局の破損が無くても、桁違いの輻輳による、発信規制もかかるでしょう。それを踏まえて、連絡を取り合えなくても、「てんでこ」で、どこに居たら、どこに避難するかと家族で決めておくのが、いいのかもしれません。この本でも、自分だけで避難する割り切りの様子が描かかれています。
実際、図書館の貸し出し状況を見ても、入庫以来、ほとんど借りられていません。
猪瀬氏がどうこうとか、内容がどうという以前に、どんなに「いい話」だったとしても、まだ、つらい過去に向き合える気持ちになれない、というのも事実なんではと思います。
ただ、防災の原点を振り返るという点では、意味のある本だと思います。津波や避難の様子が受け止められるようになったら、一度振り返るのは、将来のために、やっておくべき事のように思えます。